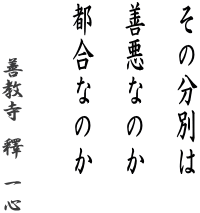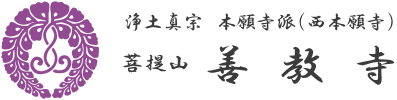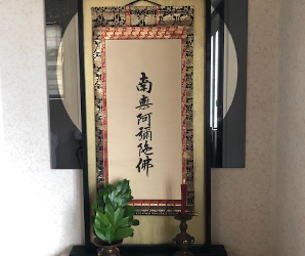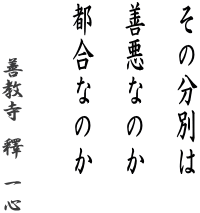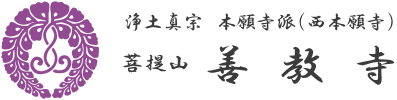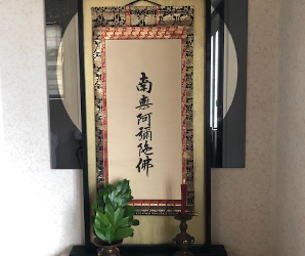新しい年が明け、皆さま健やかにお過ごしのことと慶賀に存じます。
今年はついに善教寺が完成し、やっと本堂でのお勤めができるようになります。(はず)
派手な落慶法要はいまのところ予定はしていませんが、質素にお披露目会的な行事は行おうと考えています。
また、お寺が出来たことで新しいお寺の運営方法もしていこうと考えています。
今、お寺の世界って「跡継ぎ問題」が深刻なんです。
善教寺も実はそうで、私には子供がおりませんので、一般的に「子供に継いでもらう」ということはできません。
私は外からお寺の世界に入ってきましたので、一般的な寺院運営について「常識」も「非常識」も持ち合わせて
おりません。
あるのは「形や慣習などにとらわれることなく、如何にお寺を発展させ、続けていけるようにするか?」という
アイデアだけです。
皆さまご存じのようにお寺って「宗教法人」です。
(全てのお寺がそうではありませんが、大多数のお寺は宗教法人です)
法人格を持っていますから、「個人」ではなく「人の集合体」です。
言ってみれば一般の会社と変わりはありません。
血縁関係であろうとなかろうと、有能な人が集まって仕事をしていくから、その会社の業績は伸びてゆく…
それが普通です。
でもお寺って法人格を持っているのにも関わらず、なぜか「家単位」で運営しようとします。
これだと、息子が継がない、娘が継がない、となったら即「跡継ぎがいない」という問題に直面します。
それは家業として続けていかなければ、という考えにこだわるからです。
なぜ家単位で、血縁関係で続けていかなきゃならないのでしょうか???
外から入ってきた私にはそれが理解できません。
しかも善教寺は元々「本田善教(ほんだよしのり)卿」が建立し、以後400年以上にわたって「本田家」
が守ってきましたが、私が住職となったので、既に「本田家」でもありません。
なので私は善教寺を継ぐと決めた当初から「たくさん善教寺で僧侶を育て、普通の会社のようにお寺を運営
していく」と考えていました。
しかも、育てていく僧侶はお寺の世界に元々居た人ではなく、私のように全く別の世界から仏門入って
もらいたいと考えています。
その方がより視野が広く、在家で暮らす門信徒の皆様と同じ感覚を持てるからです。
(全ての寺族が視野が狭い、という意味ではありません。俗世間での感覚の話です。)
でも以前「たくさん外からの僧侶を育てる!」と僧侶仲間に話したことがありましたが、これを真っ向否定
されました。
「どうして?なんでそんなことをするの?僧侶を量産するってどういうこと?」と、なんか嫌悪感を持って
言われました。
でもなぜそれがいけないのか私には全くわかりませんので「では何がいけないのか?」と聞きましたが
「それは非常識だと思う」とバッサリ言われました。
今度は「じゃあ、何がどう非常識なのか?」と再度聞きましたが「そんなこと聞いたことがない」としか
返答をもらえませんでした。
そこ!そこなんです!
その世界に長く居ると、聞いたことない、やったことない、という事に対して拒絶反応を起こすんです。
だから、別の世界からの、新しい考えを持った人たちを迎え入れて運営していかないと跡継ぎ問題や
お寺離れといった問題が解決どころかより深刻になっていくばかりなんです。
それに何よりも、子供のいない私には、誰がなんと言おうと、そうしていくしかないんです。
でなければ、せっかくお寺を再建したのに、善教寺は私の代で終わってしまいますから。
なので、お寺が完成したら善教寺の僧侶をたくさん募集し育てていきたいと思っています。
善教寺が熊本地震で全壊した翌年、浄土真宗本願寺派のご門主が更地になってしまった善教寺にお見舞いに
来て下さいましたが、この時私はご門主と握手しながら「優秀な僧侶をこれからたくさん育てます!」
と断言しています。
この時ご門主は「はあ…」というリアクションでしたけど…
それはさておき、そんな目標を持って善教寺の運営をして参ります。
皆さま、本年もどうぞ宜しくお願い致します。
さて、今年最初の法語は「善悪の定義」に触れてみました。
私たちは何か見聞きするとすぐに分別(ふんべつ)します。
それは「好き嫌い」「高い安い」「広い狭い」など、分けて考える思考があるからです。
悪い事ではありませんが、これらは自分の持つ「モノサシ」を定義として決める、ということを
忘れてはいけません。
我ら凡夫が「善悪」を語るのは実は大変困難な事なんです。
以前もこの場で触れたことがありましたが、皆さんは善人ですか?悪人ですか?という質問に対して、
どちらに手を上げますか?
「善人と言えるほど立派な生き方はしていなし…かと言って悪人のような悪いこともしていないし…」って
いま考えていますよね?
そうなんです。
いつもすぐに分別をして考えるのに、いざ自分のことになると自分自身の分別が付かないのが我ら凡夫
なんですね。
ではもう少し話を簡単にして…皆さんの中で「あの人はいい人だ」という人、頭に浮かびますか?
ではその人は「なぜいい人なのか?」を自分で説明できますか?
また逆の話で「あの人は嫌な人だ」という人もおられると思いますが、その人の顔を思い浮かべて
「なぜ嫌な人なのか?」はどうでしょう?
「難しいこと聞いてくるなよ」と思ってますよね?(笑)
これらの善だ悪だ、良いだ悪いだ、好きだ嫌いだ、って誰が「決めていますか?」というのがここでの本題です。
決めているからには決めるなりの定義、モノサシがあります。
しかし人間の持つこの定義、モノサシが実に怪しい…
なぜなら、その定義、モノサシは「都合」が多分にあるからです。
あまりピンときませんか?
例えば、先にも出てきた「いい人」。
なぜ「いい人なのか?」を考えた時に頭の中にいろいろ浮かんだはずです。
「いつも親切」、「いつも優しい」、「いつも笑顔で接してくれる」、「いつも困った時に助けてくれる」
…いろいろあると思いますが、ある時突然この人に怒鳴られたとします。
途端にこの人は「幻滅したー。もう嫌な人」入りですよね?
しばらくして、その怒鳴られた理由が自分では全く気付いてなかったけど、実は自分がとても危険な目に
遭うところで、その人が怒鳴ったおかげで立ち止まり、脇を信号無視の自転車が猛スピードですり抜けて
行った…でも自分は怒鳴られたことで固まってしまい、助けてもらったことにすら気付かなかった…
と知った時、また「いい人」入りしませんか?
なんか忙しいですよね。
これ、自分の都合という基準です。
私は本業でヘリコプターに乗っていますが、結構音がうるさいので時々苦情が来ます。
なので、地上の人にしてみればヘリコプターなんて自分の生活の邪魔をする騒音製造機だ、くらいに
思っているかもしれません。
一方、子供たち集まるイベントで、上空からお菓子まきをしたこともありましたが、普段よりもかなり低空で
ホバリングしますので騒音もかなり大きいですし、土埃が大きく舞って地上の人は砂まみれ…
でもこんな時、子供も大人もみんな手を振って喜んでくれます。
結局、人は都合というモノサシで何かを測り、その時の都合で好きは嫌いになり、嫌いは好きになり
という曖昧な定義で見ている、ということです。
しかし、先ほどの「みなさんは善人ですか?悪人ですか?」という話になると、自分にモノサシを
当てはめられない…つまり自分自身に都合は当てられないので「どちらでもない」となるんです。
お釈迦さまは人のこんな曖昧さを見抜き、「中道(ちゅうどう)」という教えを残されました。
(中庸“ちゅうよう”という教えもありますが、これは儒教の教え)
人は物の見方を分別し、右か左か、イエスかノーか、敵か味方か、と極端から極端へ当てはめがちです。
実はこれもストレスの原因になったりします。
お釈迦さまはこんな極端から極端へという思考を否定し、常にバランスを大切にすることを説かれました。
実はそれが、私たちが一番生きやすい道だったんです。
中道は、右とか左とかには属さず、自由な位置を保ち、両極から離れで矛盾対立を超える事。
極端な苦行をして生きるのではなく、また快楽に浸って生きるのでもない。
わかりやすく言えば「良いかげん」(いい加減ではなく…)や「良い塩梅」といった状態であることです。
私は以前国立大学にゲスト講師として招かれて講義をしたこともありましたが、必ず学生さん達にこう
言ってました。
「皆さんが社会に出て最初に学ぶことは何だかわかりますか?」と。
すると「仕事のスキル」だとか「社会での役割」だとか、「民主主義とは何か」とか、まあさすが国立大学
の学生さん達だな、という回答が出てきます。
しかし私はこう言います。
「どれも間違い。皆さんが社会で最初に学ぶのは矛盾と理不尽だよ」って。
なぜなら、子供の頃から彼らのような学生の歳まで、親や学校から学ぶことは実は「白」と「黒」
ばかりなんです。
つまり「正義」とされる正しい事、理想的な人間像などを「白」として学び、「悪」とされる
違法的な事、道徳に反する事を「黒」として避けるように躾けられ、常に白側の生き方をして
黒には近付かないことが正しい事、と教えられるからです。
でも実際にこの世の中には完全な白、完全な黒で生きることは不可能で、本当は一人残らずその間の
グレーな世界で生きる事になります。
白と黒の境界線がいきなり無くなるんです。
その中で自分はどうやって生きていくのか、を考えるのに白だ黒だを捨てないと自分が苦しくなる
だけなんですね。
だから中道の生き方が大事になっていくんです。
善だ、悪だを論じる前に、人は誰しも善であり、悪でもあり、その間でしか生きられないことを知る。
だからこそ、都合で善だ悪だと考えてしまうのはやめて、冷静にバランスを保ち続けることを知る。
これがお釈迦さまの悟られた真理、悟りの一つです。
「そんなの、どっち付かずで、ずるくないか?」と、もし思われたのなら「そう考えないといけない」
という、これまた誰かの都合を知らない間に刷り込まれているのかもしれません。
それをリセットするのが中道の教えであり、11月のここでの法話でご紹介した「四苦八苦」しながら
生きる私たちが「苦」を滅する為の四諦八正道(したいはっしょうどう)の教えへと、つながっていきます。
四諦八正道については、また近いうちにこちらでご紹介させて頂こうと思います。
皆さま、今年もどうぞ慈光照護のもと、益々ご健勝にてお念仏相続されますよう、念願しております。
南無阿弥陀仏
南無阿弥陀仏
善教寺 住職
本願寺派 布教使
釋 一心(西守 騎世将)